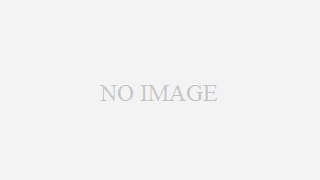 妖は宵闇に夢を見つ
妖は宵闇に夢を見つ 一章 終の涯(六)
──いつも、いつもひもじかった。 身体のどこかしらがいつも痛んで、生傷の絶えたことはない。いつも喉が渇いていて、背中とくっつきそうなくらいおなかがすいていた。 骨と皮ばかりに痩せて節の目立つ、枯れ枝のような手脚を持つ小さな身体。生来は白い白...
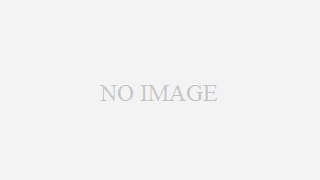 妖は宵闇に夢を見つ
妖は宵闇に夢を見つ 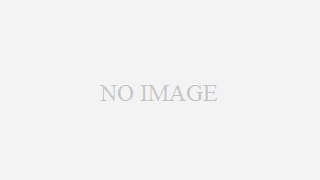 妖は宵闇に夢を見つ
妖は宵闇に夢を見つ 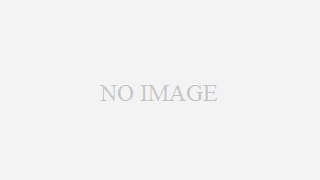 妖は宵闇に夢を見つ
妖は宵闇に夢を見つ 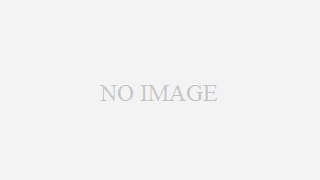 妖は宵闇に夢を見つ
妖は宵闇に夢を見つ 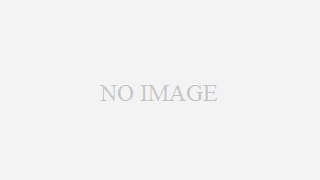 妖は宵闇に夢を見つ
妖は宵闇に夢を見つ